


若い先生たちが最前線でやっている姿を見て、自分もここに続きたいと思った〜消化器内視鏡センター・後編〜

名方勇介が千船病院を研修先の選択肢に入れたのは、岩手医科大学医学部卒業前の、2014年頃だった。千船病院の病理診断科の医師である父親から、内視鏡手術を専門とするならば、自分の病院も悪くないと薦められたのだ。
名方は1989年に兵庫県西宮市に生まれた。祖父、父親と医師の家系である。
早くから医師になるつもりだったのかと問うと、大きく首を振った。「ぼく、医者になるの嫌でした。結構、頭、悪かったんです。父親からはお前の頭じゃ医学部なんか入れへんって言われていました。高3から予備校行ったんですけれど、こんな自由な時間があるんやって遊んでました」
2年間浪人した後、岩手医科大学医学部になんとか滑り込んだ。受験はほんまに苦手でした、未だに入学試験に落ちる夢を見ますと、名方は頭を掻いた。「医学部の1年目っていうのは数学とか教養課程なんです。そのときは留年しそうなぐらい成績が悪かった。2年生になって解剖が始まると面白くなってきた。4年生から臨床(実習)に入って、各科の基礎をやっていくんです。実習に行くのは無茶苦茶楽しかった。上の先生から〝お前、やってみるか〟と言われたら、チャンスやと思って、どんどんやらせてもらいました」
医者の家系で半ば強制的ではあったにしても、医学部に来て良かったと思った。岩手での生活は気に入っていた。そのまま残ることも考えたが、これまで世話になった家族のため関西に戻ることにしたのだ。「(千船病院の)内視鏡センターが盛り上がっているというのを父から聞いていました。若い先生たちが最前線でやっている姿を見て、自分もここに続けたらいいなと思いました」
2015年4月、名方は専攻医として千船病院に入職、病院に近い寮に住むことになった。「病院から歩いて5分ぐらいのところにある、昭和な感じのアパート、ワンルームです。仲のいい先輩が近くにある社宅に住んでいて、その人がオンコールで呼ばれたときはぼくも一緒に行っていました。先輩の横に立っての介助ですね。夜中に呼ばれたら人も少ないので看護師さんと一緒にやっていました」
もちろんオンコール対応に付き合うのは専攻医の義務ではない。「やれとは言われたこともないし、嫌々でもなかった。早く仕事を覚えたいという気持ちがありました。消化器内科は患者さんのためにみんなでやろうという雰囲気があったんでしょうね。先輩が呼ばれたら、当然のようにぼくも行くという感じでした」
初めて止血をした患者のことを今もよく覚えている。「無茶苦茶、血を吐いた45才ぐらいの若い患者さんが運ばれてきたんです。胃カメラで調べたら、胃潰瘍ができていて、そこから出血していた。その出血を初めてきれいに止めることができたんです」 その患者は血を吐いたことがきっかけで、がんが見つかり、早期治療に繋がった。怪我の功名だった。
2年間の研修期間の後、2017年4月に名方は正式に診療部消化器内科に入った。先輩医師に交じって内視鏡手術を積み重ねるうちに、改めて船津の凄さに気がついた。
例えば、止血――。 内視鏡から止血用クリップと呼ばれる医療用ホチキスを入れて、血管を挟み込んで出血を止める。「内視鏡カメラで映る画面自体は大きい。画質もいいんです。でも、カメラをどう動かすかによって見え方が変わってくる。処置部をきちんと把握した上でクリッピングしなければならない。自分がやっていてなかなかできなくて時間が掛かってしまう患者さんでも、船津先生に代わるとすぐにできてしまう」
内視鏡のカメラが映し出す映像は2次元、また内臓の形には個体差がある。内臓の構造を知悉した上で、奥行き、厚みなどを計算して、鉗子を正確に、そして素早く動かさなければならない。
治療はもちろん大切ですけれど、トータルで患者さんを診られる医者になりたい
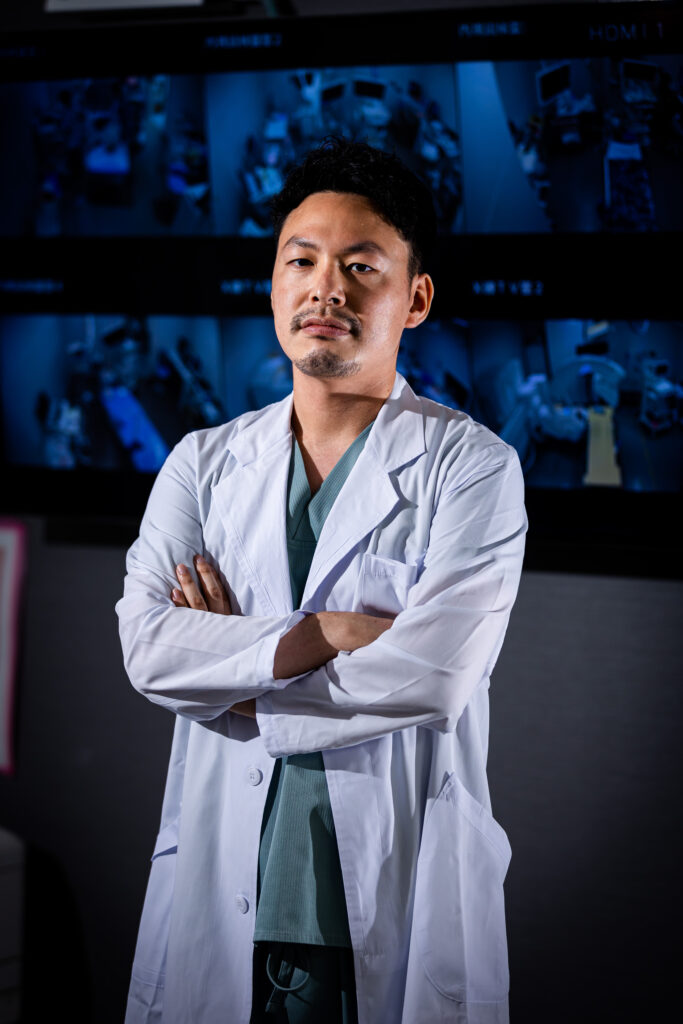
2017年7月、千船病院は阪神電鉄福駅そばに新病院となって移転した。船津は新しい内視鏡センターの設計から関わることになった。「また設計図の魔法に引っかかった」と船津は言うが、彼のこだわりは十分に反映されている。
通常の内視鏡機器の他、小腸バルーン内視鏡、カプセル内視鏡、胆膵疾患の処置に使用する胆道鏡や電気水圧衝撃波結石破砕装置などの特殊内視鏡機器を設置。内視鏡検査室はプライバシーを守るためにすべて完全個室。壁紙にもこだわった。「患者さんにとって検査、手術ってしんどい。だから綺麗な環境で、変な表現ですけれど、ちょっと高級感があれば、少しでも心が軽くなる」
新病院となった後も船津は単身赴任生活を続けている。彼が考え続けているのは、いかに地域に密着した高度な医療を提供するか、である。「ドクターってつっけんどんで偉そうで、というところがあると思うんです。でもそんなんは絶対嫌なんです。患者さんにとって話しやすくてなんでも相談できる、親身になってくれる消化器内科医でありたい。うちの医師にはそういう風になって欲しい」 今も彼の頭に浮かぶのは前出の、初めて担当した女性のことだ。「あのときぼくは研修医で何にもできなかったんです。毎日顔を見に行くことしかできなかった。年も違うし、ぼくはアホやし話が合わへん。毎日、聴診器を当てて、血圧測って、同じことをするしかなかった。それでもぼくが行くと暖かく迎えてくれて、孫みたいに大事にしてくれた」
彼女が退院するとき、船津は「ぼく何もできませんでしたけど、ありがとうございました」と頭を下げた。すると「先生が一番話を聞いてくれた。話をしていると元気になれた」と微笑んだ。「次、入院したときも先生に主治医になってもらいたいって言ってくださった。それがすごく嬉しかった。処置をするのも大事ですけれど、心を通わせるケアができるようになりたいというのがぼくの根底に流れている」
千船病院は小さくはないが、大病院ともいえない。だからこそ、地域に根ざした医療が実現できるはずだと船津は信じている。「世界には、お金に糸目をつけなければ、まだ普及していない最先端の治療、最高の治療を受けられる場所があるかもしれない。千船病院でそれはできなくても、現状のガイドラインで定められている最良の治療はできるし、やらなきゃいけない。わざわざそういうところに行かなくても、千船病院で先生に診てもらいたいという医師にならないといけない」
まだまだあかんところもあるんですけれど、やろうと思えばここは変えられる、可能性があると思っているんですよと、自らに言い聞かせるように呟いた。その思いは、後進の名方たちにしっかりと引き継がれている。「内視鏡をはじめた頃は、血を止めることがものすごく気持ちよくて、楽しかった。そこにやり甲斐を感じていました。でも何年か過ごすうちに、患者さんの人生、背景を見ることが大切だと思うようになってきました。治療はもちろん大切ですけれど、トータルで患者さんを診られる医者になりたい」







