


減量手術チーム 減量はしんどい。 だからこそ、チーム医療が必要~前編~

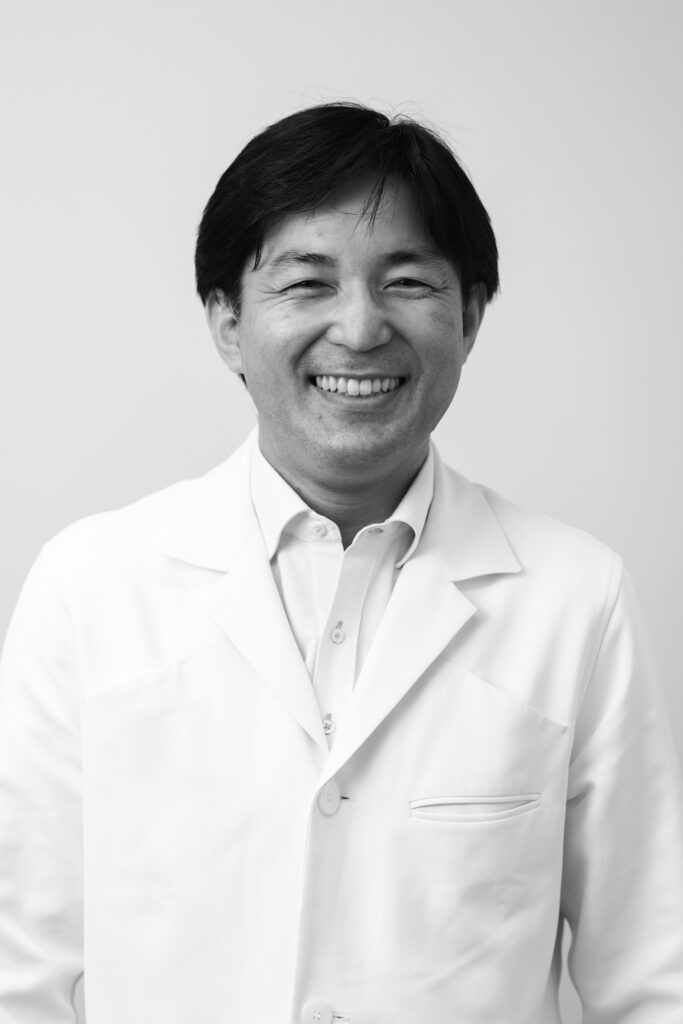
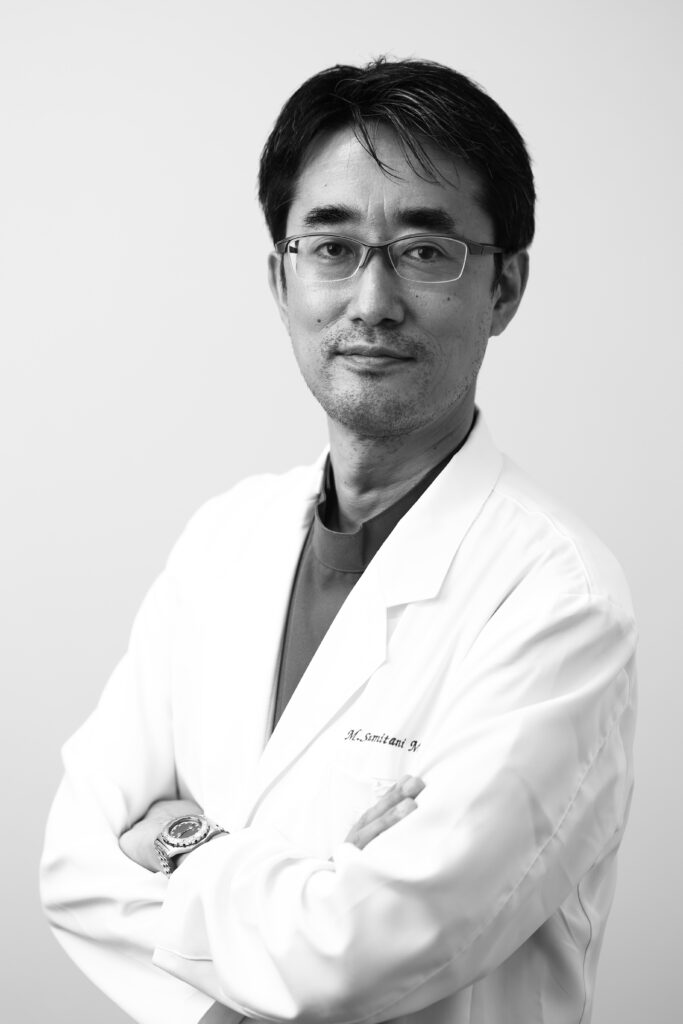


上段左から
栄養管理科主任 管理栄養士 田中理恵子、肥満・糖尿病内分泌センター長 北浜誠一
呼吸器内科部長 住谷充弘
下段左から
糖尿病内分泌内科部長 中島進介、医事科主任・減量コーディネーター 平井麻衣子
8 割程度を切除して胃を小さくすることで、平均30 パーセント程度の体重が減少する——。これだけ聞くと肥満に悩む方にとっては夢の手術のように映る。現在主流となっている「スリーブ状胃切除手術」自体の難易度は高くないという。重要なのは術前から術後までのケア。まさに「チーム医療」であるのだ。
ある日の午後4時、千船病院の会議室で外科医や内科医など計11人が参加してカンファレンスが始まった。モニターに映し出されたのは、40代男性のプロフィールだ。身長184センチで体重155キロ。診察した肥満・糖尿病内分泌センター長の北浜誠一は、「本人はなんとか痩せて、パートナーと一緒にジェットコースターに乗れるようになりたいと前向きに頑張っています」と報告した。
続いて報告されたのは、ストレス解消を食事に求めて肥満になった女性や、何度も減量に挑戦したがうまくいかず、一縷の望みをかけて来院した女性――。
これらの患者たちに共通しているのは、減量手術を希望している点だ。
減量手術の主流である腹腔鏡下スリーブ状胃切除術は、体に小さな穴をあけて特殊な器具を挿入。胃の8割程度を切除して、細長く縫い合わせる。術後1年〜1年半で平均30%程度の体重が減少するという。
肥満に悩む人にとっては夢のような手術だが、望めば誰でも受けられるわけではない。スリーブ状胃切除術は保険診療だが、保険適応になるには細かな条件がある(表参照)。また保険適応になっても、リスクが高かったり、術前の行動変容が見られず減量効果が見込みづらい場合は病院としてゴーサインを出せない。
この患者は本当に手術を受けたほうが幸せになれるのか。治療に関わる医師や管理栄養士、理学療法士などで構成される「減量チーム」が一堂に会して議論していたのも、手術の適応を判断するためだった。
————————————————————————————————
●腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の適応条件( アかイのどちらかを満たす必要あり)
(ア)6ヶ月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMI(ボディマス指数)が 35 以上の肥満症の患者であって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症又は閉塞性睡眠時無呼吸症候群のうち 1つ以上を合併しているもの。
(イ)6ヶ月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが 32 ~ 34.9 の肥満症の患者であって、以下の2つ以上を合併しているもの。
・糖尿病 ヘモグロビンA1c が 8.0%以上(NGSP値)
・高血圧症 6ヶ月以上、降圧剤による薬物治療を行っても管理が困難(収縮期血圧160mmHg 以上)なものに限る。
・脂質異常症 6ヶ月以上、スタチン製剤等による薬物治療を行っても管理が困難
(LDL コレステロール 140mg/dL 以上又はnon-HDL コレステロール 170m/dL 以上)なものに限る。
・閉塞性睡眠時無呼吸症候群 AHI(無呼吸低呼吸指数)≧30 の重症のものに限る。
————————————————————————————————
減量手術の先進国、アメリカで見たチーム医療
千船病院は、日本肥満症治療学会が肥満外科手術実施施設として認定した17施設の1つである。2016年に糖尿病・減量外科を開設して以降、実績を重ねて症例数は累計400件(2022年7月現在)に達した。2021年度の手術件数は100件で全国2位を誇る。
千船病院を日本有数の減量外科施設に引き上げた中心人物が、減量チームを率いる北浜だ。
北浜は京都大学医学部時代、がん研究の道に進むつもりだった。しかし、実習先で知り合った医師が献身的に患者に接する姿を見て臨床に舵を切った。
外科医になり、日本における腹腔鏡手術第一人者のもとで腕を磨いた。ただ、腹腔鏡手術のトレーニング制度はアメリカのほうが進んでいる。もっと上手くなりたいという一心で渡米し、フェローシップ先で出会ったのが減量手術だった。
「病院の受付の方がほっそりスリムな人でした。うかがうと、その方も減量手術の経験者。当時、減量手術は日本で年間50件程度でしたが、私が勤務した病院では週15件行うほどハイボリューム(件数が多い)。将来、日本でもメジャーな手術になると確信しました」
アメリカで見えてきたことがもう1つある。チーム医療の重要性だ。
「日本は数が少ないので、医師が患者さん1人ひとりに時間をかけて診ることができました。一方、アメリカはハイボリュームなので、多くの専門職が関わって分業しないと対応できません。将来、日本で減量手術が広がるなら、チーム医療体制の構築が必要だとも感じました」
日本に減量手術を根づかせたい――。北浜はアメリカで3年間学んだ後、帰国して減量外科を立ち上げるために東奔西走する。2つの病院で実際に開設したが、さまざまな事情で軌道に乗らなかった。 三度目の正直で巡り合ったのが千船病院だった。
「話をいただいて面接に行っても、現場から『切らんでも内科的治療で十分』『万が一事故が起きたら大問題』と反対の声があがることが多い。しかし、千船病院は外科部長はじめ、内科や栄養科の先生、事務方もみなで『おもしろそうやね』とサポーティブ(協力的)でした。糖尿病の先生もいらっしゃるし、減量のチーム医療をやるならここだなと」
「できるだけ切りたくない」内科医が考えを変えた理由
2016年、北浜は千船病院で糖尿病・減量外科を立ち上げる。減量手術に限らず、チーム医療の鍵となるのが外科と内科の連携だ。一般的に内科は「切らずに済むなら切らないほうがいい」と考える傾向がある。この壁を乗り越えるため、北浜は自分が最初に診察することにこだわった。
「多くの病院は、まず内科の先生が診て、手術以外に選択肢がない患者さんを外科に送ります。このやり方では、たとえ内科の先生がサポーティブでも手術にいたる患者さんは増えません。減量外来のファーストタッチは必ず私が診ます」
だからといって北浜が手術へ前のめりになっているわけではない。チームの一員である糖尿病内分泌内科部長の中島進介は、「北浜先生はすごく慎重」と明かす。
「減量手術後しばらくは特殊な食事しか食べられません。それを無視して普通の食事をすればリスクがあります。北浜先生は患者さんが約束を守れる人だと確信を持てなければ、たとえ保険適応の条件を満たしていても手術をしない。はじめから手術ありきではないから、私たちも率直に意見を言えます」
今でこそ減量手術に協力的な中島だが、千船病院に来る前は、健康な人の胃を切ることに否定的だったという。
中島は鹿児島大学医学部を卒業後、千船病院で初期研修を行い、「全身を診られる医者になりたい」と内科を選択した。神戸大学医学部附属病院で糖尿病内分泌内科医として研鑽を積み、2019年、7年ぶりに古巣の千船病院に復帰した。肥満関連疾患の治療を数多く手がけて内科医として自信をつけた中島が、「減量外科の存在は知っていたが、前向きにはとらえていなかった」と考えるのも無理はなかった。
千船病院に戻ってきたとき、すでにチーム医療の枠組みはできており、気乗りしないままチームに加わった。しかし、減量手術を受けた患者を診察して考えが変わった。
「インスリンを1日100単位以上打っていた糖尿病患者さんがゼロになっていました。他の患者さんもだいたい薬が大きく減っている。信じられず、『こんなにたくさんの薬を一気にやめて大丈夫ですか』と同僚の先生に聞いてしまったくらいです」
効果を目の当たりにしてから、積極的にチームに関わるようになった。症例が積み重なり、手術に踏み切った人とそうでない人の生命予後や薬価の比較もデータで検証できるようになった。中島の中で減量手術は、いまや「患者さんにすすめていい治療」という位置づけになった。

取材・文 村上敬 写真 奥田真也






