


千船病院は小さくはないが大病院でもない。だからこそ地域に根ざした医療ができる。〜消化器内視鏡センター・前編〜

消化器内視鏡センターは24時間対応、夜間休日であっても内視鏡手術が可能である。困った人がいれば助ける、可能な限り患者を断らない――千船病院の哲学がはっきりと現れている部署でもあるのだ。
思っていたんと全然違うやん、と船津英司は思わず呟いた。
2008年4月、千船病院は船津を迎えるにあたって、消化器内視鏡センター(以下、内視鏡センター)を新設することになっていた。一度、現地を見てみようと足を運んだのだ。そこは窓のない10畳ほどの部屋だった。ここに内視鏡室、洗浄室、待合室を作らなければならない。かなり狭い。話が違うのではないかと、船津は案内してくれた病院関係者に、ややとげのある調子で訊ねた。すると相手は「お渡しした図面通りの部屋ですよ」と事もなげに返した。「図面ってね、魔法みたいな感じでめっちゃ広く感じるんです。先生、よく見てください、図面って縮尺があるんですよって。確かにその通りなんです。うわ、この広さでやるのはきつい、というのが最初の感想でした」
センターの立ち上げメンバーは、船津、そして専攻医の2人。専攻医とは初期研修を終えた後、専門研修プログラムで学ぶ医師のことを指す。かつては後期研修医と呼ばれていた。
この内視鏡センターでゆくゆくは医師、専攻医を広く迎え入れるつもりだった。優秀な医師たちを惹きつけるには、魅力的な環境を整えることが必須である。そこで関西地区では珍しかった超音波内視鏡という最新機器を導入していた。機器はともかく、物理的な広さが足りないと船津は暗い気持ちになった。
旧知の医療機器メーカーの担当者たちが「先生、内視鏡センターを作ってもらったらしいですね」と顔を出した。彼らは、部屋を一瞥(いちべつ)すると、商機がないと判断したのか、ため息まじりに「また来ますね」と帰って行った。「一時期は凹みましたね。ここで1年か2年やって、大学病院に戻ろうと思っていました」
船津は1973年に京都市で生まれた。父親は東映太秦映画村のすぐそばでオートバイ店を営んでいた。子ども時代は機械いじりが好きで、いずれは工学部で学び、ロボットを作ってみたいと朧気に考えていた。「うちのお袋が、工学部に行ってロボットとかいじったりしていると、あんた引きこもりになるで、人と接する仕事をせなあかんっていうんです。確かにオタクみたいなところがありました。それで人を治すのも面白いかなと思うようになって、そのときの学力に合った、京都府立医大に行くことにしました」
京都府立医科大学卒業後、京都第一赤十字病院で研修医として歩み始めた。研修終了後は、がんの研究をするつもりだった。「第一日赤(赤十字病院)の消化器内科部長の兄弟子に当たる方が、日本で初めて十二指腸乳頭切開術をした先生だったんです。そうした関係で第一日赤は消化器内科が有名でした。消化器のがんって多いじゃないですか。それで消化器内科はいいなと。内視鏡という器械をいじったりするのも好きでしたし」
内視鏡手術とは、口から内視鏡 ―内臓や体腔の内部を観察する機器 ―を挿入して行う手術のことだ。カメラと強い光源により、体内を明るく照らし、鉗子や処置具を操作して手術を行う。開腹手術と比べると身体への負担、つまり〝侵襲〟が少なく、術後の回復が早い。
最初に担当したのは、胃がんをわずらった年老いた女性だった。「胃がんで胃が狭くなっていたんで、ご飯を食べられへんかったんです。そのときちょうど、ステント留置っていう治療が出てきたときだったんです」
彼女は内視鏡手術で金属製のメッシュ構造をした筒状の医療器具を患部に置き、消化管を広げる「消化管金属ステント留置術」を受けることになった。「それまでご飯を食べられなくて点滴していたおばあちゃんがご飯を食べられるようになった。すごく喜んでくれたんですね。これから内視鏡で色んなことができるようになっていくだろう。それで消化器、内視鏡医になろうと思ったんですね」
内視鏡手術の技術を上げるには、多くの患者を治療し、経験を積むことだ。第一赤十字病院の救急科では、各科の医師が持ち回りでオンコールを担当していた。オンコールとは、救急搬送時に勤務時間外であってもいつでも対応できるように待機することを指す。「オンコールをやりたがらない先生もいますよね。そこでぼくはやらせてくださいって、代わりました。さらに(医師になって)4年目ぐらいのとき、上の先生に迷惑掛けないようにしますんでって、若手の6人ぐらいの医師でオンコール表を作って回していました。朝から晩まで通常業務プラス夜間(診療)です」
1日で13人の内視鏡を使った吐血、下血の対応をしたという記録は未だに第一日赤では抜かれてへんのちゃうかなと船津は笑う。
いずれは大学病院に行く、それまでの腰掛けのつもりだった
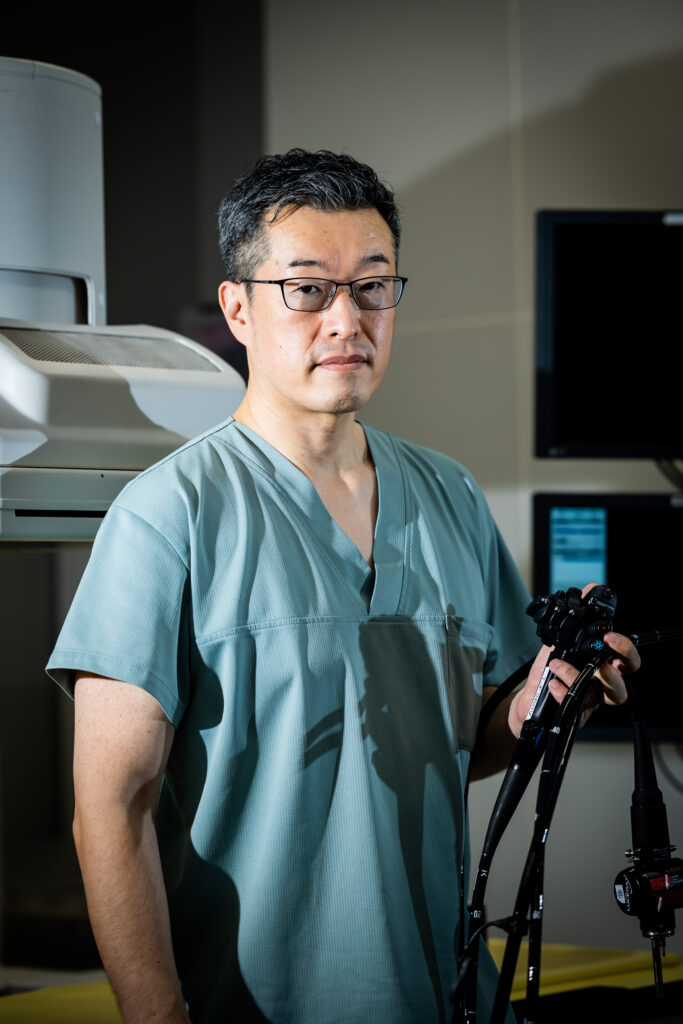
通常、外科手術は執刀医の他、助手、看護師、麻酔科の医師などチームで行う。内視鏡手術では、突き詰めれば内視鏡医、そして看護師、2人で手術が可能なことが特徴の1つだという。「自分さえやると決めたらやれる。運転にたとえれば1人でドライブしているような感じに近い。責任感は重いです。だからこそ達成感も大きい」
ある程度、自信がでてきた2007年頃、神戸大学医学部附属病院に移っていた元上司から一緒にやらないかと誘われた。そのとき、たまたま千船病院を運営する愛仁会から、内視鏡センターを立ち上げたいという相談があったという。ゼロからセンターを立ち上げるには、内視鏡手術に関する幅広い知見、臨床の経験が必要となる。そこで船津に白羽の矢が立った。いずれは大学病院に行くという約束のもと、腰掛けのつもりだった。
消化器内科の先生が2人来る、彼らがセンターを立ち上げるという話を一般内科病棟の看護師だった奈良崎由香が聞いたのは、2007年の終わり頃だったと記憶している。「具体的にどうやっていくのかは決まっていなくて、先生方が来られてから、というふわっとした話でしたから、あっ、そうなんやみたいな感じでした」
奈良崎が所属していた「四—Ⅰ病棟」が消化器内科病棟に充てられることになり、病棟内で消化器内科チームが立ち上がった。「そのとき私も手を上げたんです。手を上げたのは5人ぐらいでしたかね」
船津の第一印象は、熱い人やな、だった。「船津先生は、患者さんに対して色んな医療を提供していきたいということで、あんなことをしたい、こんなことをしていきたいって熱く語っておられた。当時の千船病院はどちらかというと年配のおとなしい先生が多かった。そんな中、ぐいぐいと色んなことを押し進めていこうとしているんだなと」
船津は奈良崎よりも4才年上の34才。もう一人の専攻医が奈良崎と同じ年だったことも親近感が増した。船津は千船病院に来るとすぐに「消化器内科カンファレンス」を始めている。患者をどのような方針で治療するのか、情報共有する会議である。医師だけでなく看護師たちも含めた多職種カンファレンスの先駆けだった。「治療だけでなく、看護師にどんな役割を担って欲しいかのレクチャーを兼ねた会にしたいというのが船津先生の考えでした。新しい治療を学ぶこともありましたし、勉強会に近い感じでした」
カンファレンスは、病棟の看護師たちに出席しやすい曜日、時間を事前に問うて「会」の日時を設定した、はずだった。「消化器内科チームに手を上げたメンバーとそうでないメンバーの温度差があったかもしれません。なかなか人が集まらなくて、結局、消化器チームのメンバーだけということも多かった」
ある日、船津と奈良崎の2人だけだったことがある。「みんな忙しいから、人集まらんよね」と船津が寂しそうな顔で言ったことが奈良崎の印象に残っている。
船津は救急医療にも力を入れた。消化器内科はオンコール体制ですべての救急患者を引き受けると宣言したのだ。船津は家族を京都に置いたまま、病院に隣接した寮に単身赴任することになった。本来は研修医が使用するためのワンルームマンションである。そして、救急患者対応の他、1日に2、3度、病棟に足を運んだ。
その熱意を意気に感じた奈良崎たち、消化器内科チームのメンバーは他の看護師たちに「一緒に話を聞こう、混じろう」と声を掛けた。気がついたときには、消化器内科チームとそれ以外の壁は消えていた。
千船病院に来たばかりの船津が「俺、ここにいるのは2年だけやねん」とうそぶく姿を奈良崎は覚えている。「その辺、全然隠すことなくオープンにしていました。最初の2年が終わる頃、今年で終わりやと言っていたんですが、1年延びた。そうしたらまた、今年で終わりやと」
そう言い続けているうちに今に至るという感じです、とくすくす笑った。








